こんにちは!弁理士のオムレツです。
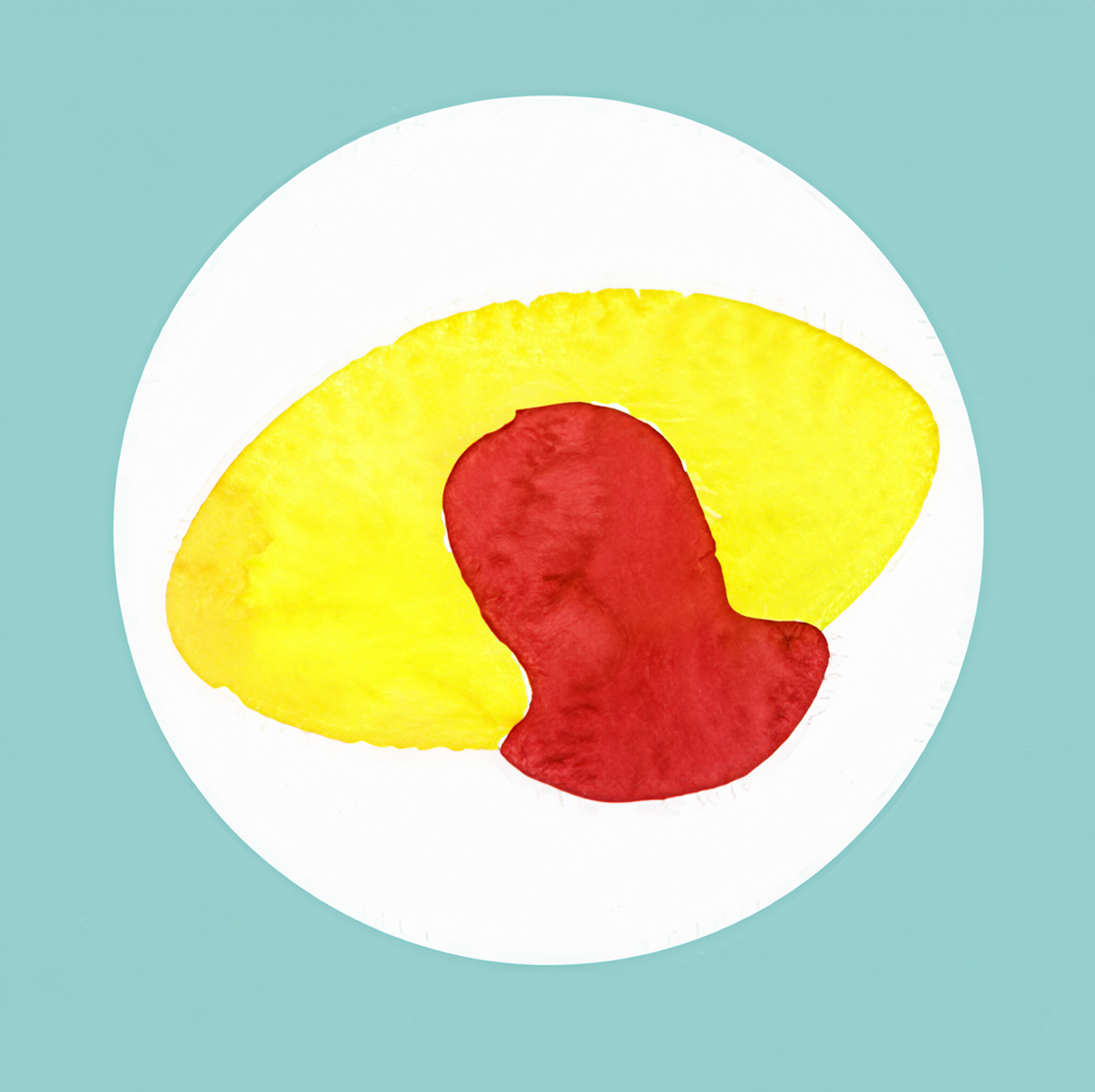
《この記事を読んで欲しい人》
特許取得を検討している人
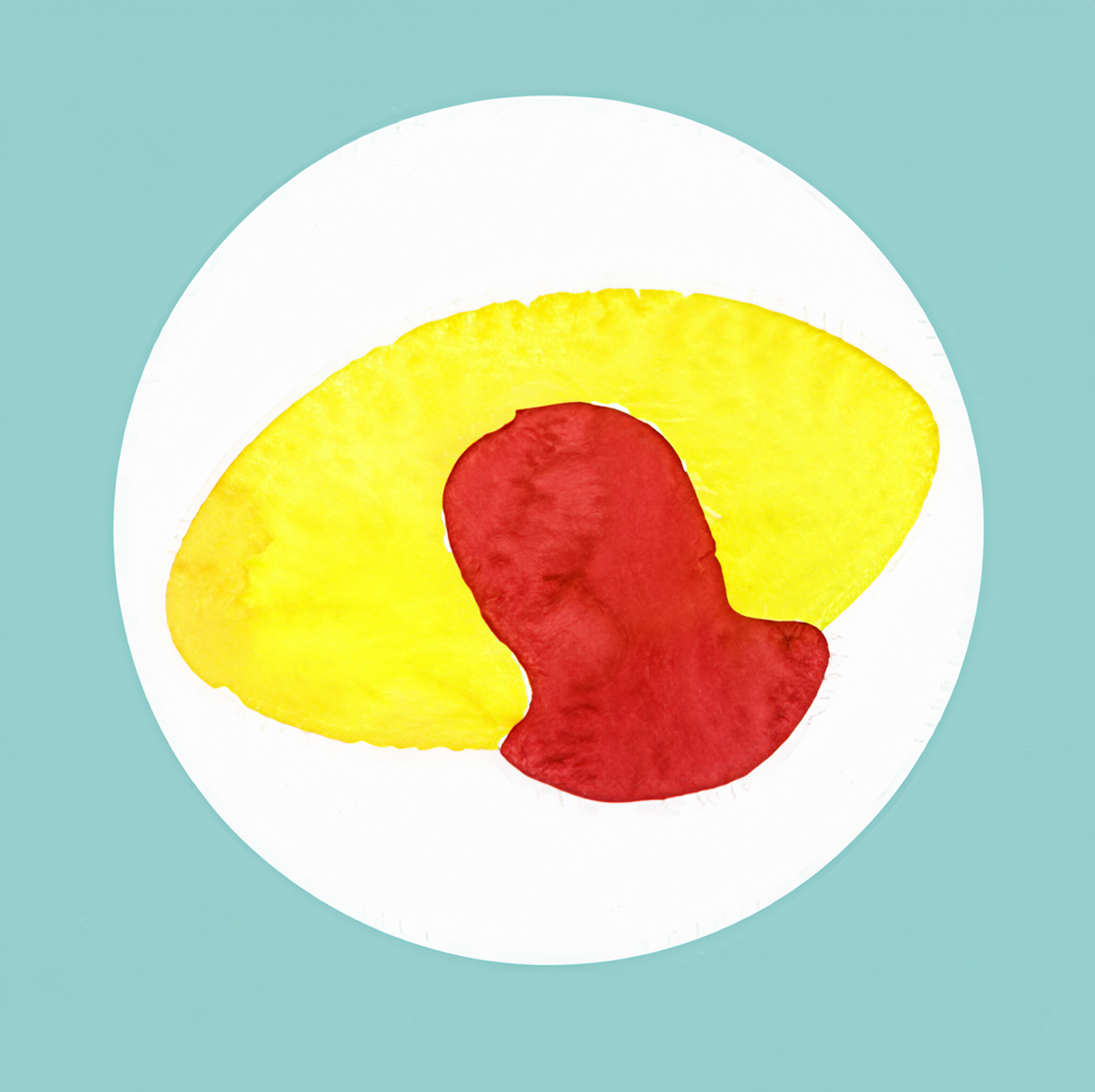 オムレツ
オムレツ《この記事を読んで欲しい人》
特許取得を検討している人
この記事では、
「特許って取る意味あるの?」「特許取得にはすごく費用かかるし、費用対効果もどれほどあるのかイマイチ分からない、、」
そんな疑問を抱えている方に向けて、特許を取得すべきか一発で判断できる『特許判断シート』を作成しました。
無料で10分で出来る!ので宜しければ是非ご活用ください!
※なお、商標(商標登録すべきか)についてはこちら↓
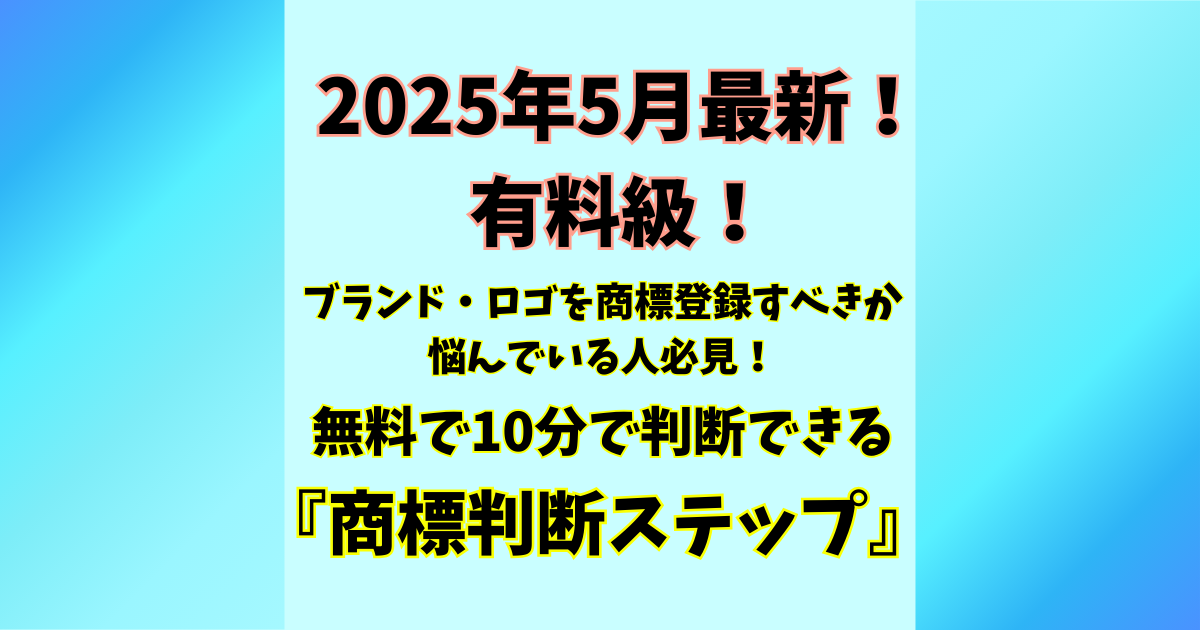
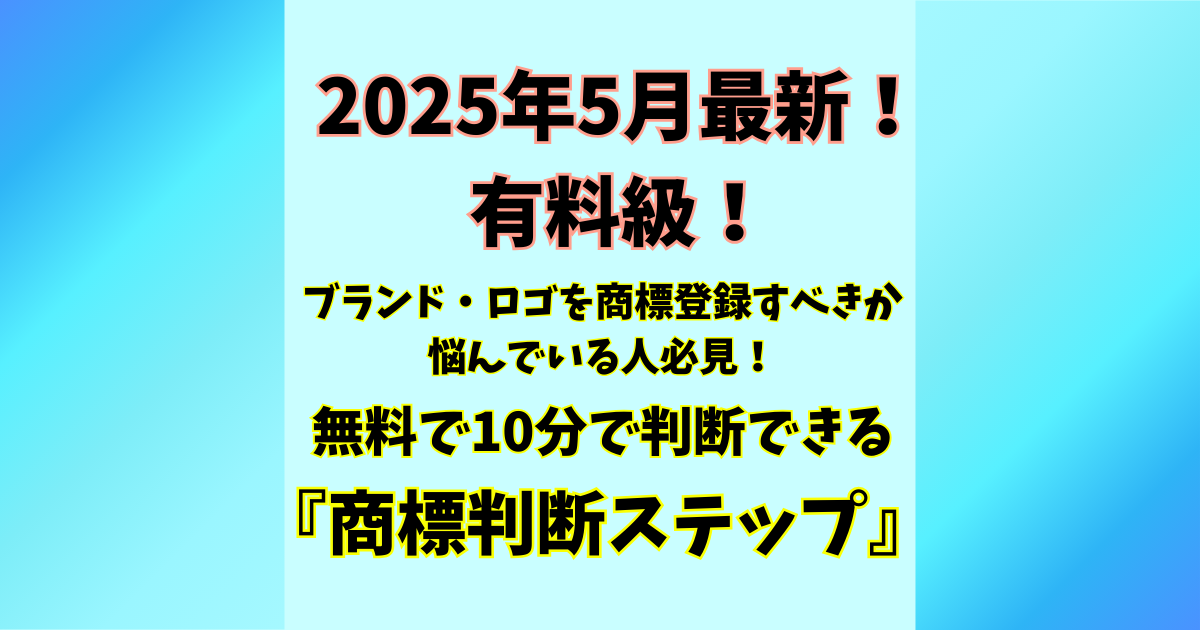
必要なもの
「特許に関係する製品・サービスの生涯予想売上」
これだけです!
例えば、製品Aが年間1000万円で8年間売れると仮定した場合には、製品Aの生涯予想売上は1000万円(年間予想売上)×8年間(継続販売予想年数)=「8000万円」になります。
なお、
・「特許が取れて他社が真似できないと仮定した場合の生涯予想売上」でお願いします。
・「特許に関係する製品・サービス」が複数ある場合には、それらの生涯予想売上の合算値でお願いします。
・継続販売予想年数が20年を超える場合は、販売開始から20年までの期間で生涯売上を算出してください(21年目以降の売上は加えないでください)。※ 特許は最大20年までしか所有できないため。
これが特許判断シート!
こちらが「特許判断シート」になります!
◎:特許取得を絶対にすべきライン(万円以上)
○:特許取得を検討すべきライン(万円)
△:特許取得の必要性が低いライン(万円以下)
| 技術分野 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| バイオテクノロジー | 4,285 | 1,500〜4,285 | 1,500 |
| 医薬品 | 3,000 | 1,800〜3,000 | 1,800 |
| 化学 | 3,488 | 2,250〜3,488 | 2,250 |
| 電子機器 | 6,000 | 3,000〜6,000 | 3,000 |
| ソフトウェア | 3,000 | 1,500〜3,000 | 1,500 |
| 自動車 | 7,500 | 3,750〜7,500 | 3,750 |
| 機械 | 5,000 | 2,250〜5,000 | 2,250 |
| 食品 | 3,000 | 1,500〜3,000 | 1,500 |
| 繊維 | 6,000 | 3,000〜6,000 | 3,000 |
使う際の注意点
使う際の注意点が1つだけあります。
それは、特許事務所に相談に行く前に必ずAIにその発明が特許になる可能性があるかを確認してください。
そこで、特許になる可能性があるとの回答を得てから、特許事務所に特許取得の相談をするようにしましょう。
AIでその発明・アイデアが特許になるかどうかを確認する方法は下の記事から!
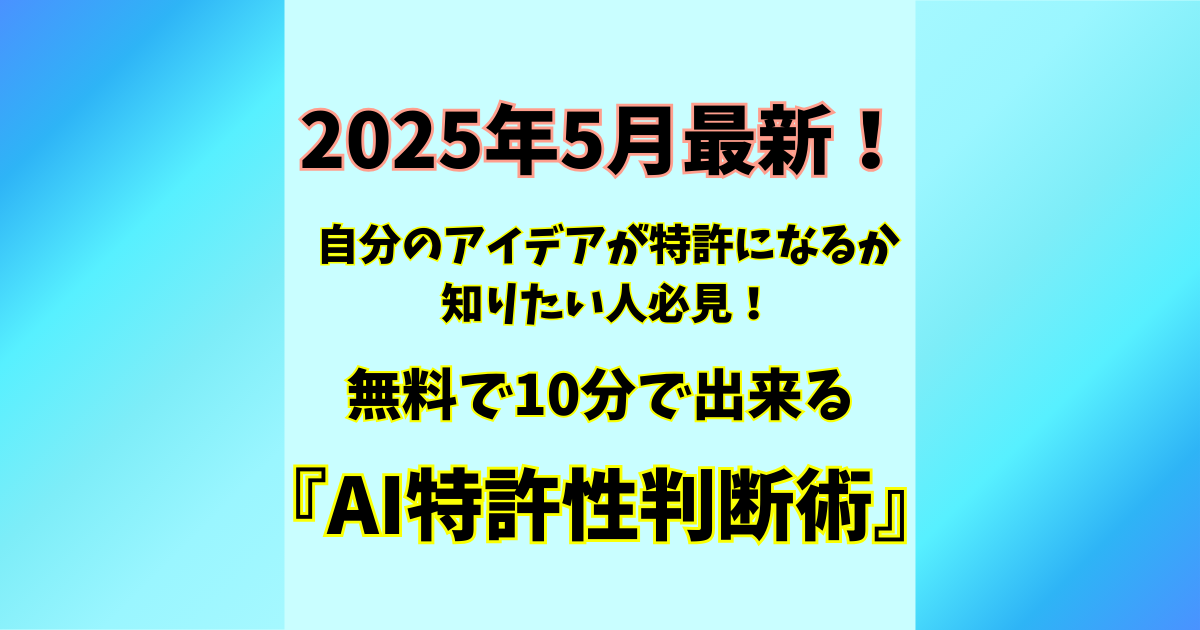
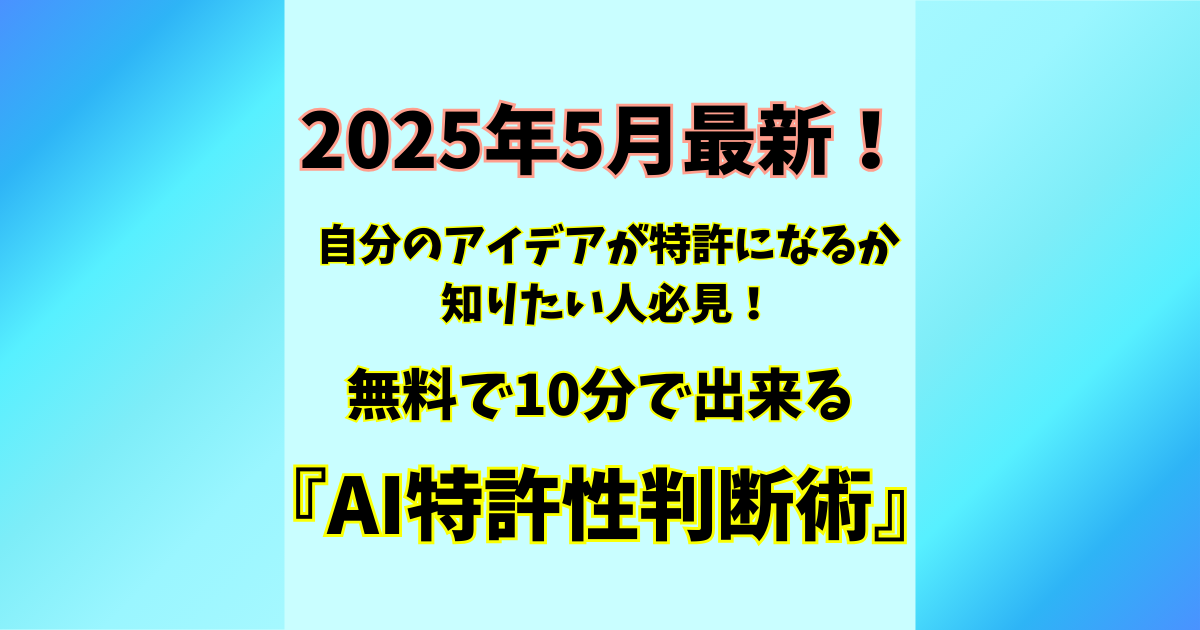
なお、発明が特許になる可能性があるかを確認する方法として、特許事務所に相談することも可能ですが、この方法は下記の2点からあまりオススメしません。
(1)客観的な判断が得られにくいから
多くの特許事務所では、たとえ特許性が低いアイデアでも、「正確には判断できませんが、出願(=特許申請)する価値はあるかもしれません」といった曖昧な表現で前向きに出願を勧めてくることがあります。理由は単純で、特許事務所は特許申請を依頼してもらうことで利益が出ますから、自分たちの収入確保のために、当然に特許出願を勧めることが予想されます。
(2)費用がかかるケースもあるから
特許になる可能性があるかを検討するための検討料を要求される場合があると考えられます。今はAIで十分に判断できるため、わざわざ特許事務所に依頼する必要もないです。
どうやって作ったの?(※ 興味のある人は読んでみてください)
1|『ライセンス料率モデル』からの算出
まず、『どのようにして「特許を取得すべき」と判断するのか?』という点についてですが、
【自社が特許取得している場合の売上】ー【自社が特許取得していない場合の売上】>【特許費用】
この条件を満たしていれば、特許費用は回収できた上で利益が出ているということですから、特許を取る意味ありますよね?
ですので、次にそれぞれのカッコ部分を埋めていきたいと思います。
1、まず【特許費用】を決定 → 「150万円」で固定
特許費用は下記の表の通りです。
※ 国内(日本)のみの平均的な特許費用(請求項10個・10年維持)より算出
| 区分 | 費用(概算) | 内容などの補足 |
|---|---|---|
| 出願費用(事務所手数料含) | 約 25〜40万円 | 書類作成、願書・明細書など |
| 中間対応費(補正・意見書) | 約 10〜25万円 | 1〜2回の対応を想定(拒絶対応) |
| 登録料(1〜3年分) | 約 2〜5万円 | 印紙代+事務所手数料含む |
| 年金(4〜10年分) | 約 90〜110万円 | 印紙代+納付手数料を含む |
| 総合計 | 約 130〜180万円 | 10年間維持した場合の全費用 |
もちろん案件によって多少費用は前後しますが、ここでは便宜上「150万円」で固定したいと思います(もし特許取得を依頼する特許事務所が決まっているのであれば、そこから見積をもらってみても良いでしょう)。
2、次に「平均ライセンス料率」から売上を算出
【自社が特許取得している場合の売上(=「特許に関係する製品・サービスの生涯予想売上」)】をPとしたとき、
ポイントは「【自社が特許を取得していない場合の売上】がどうなるか?」です。
ここで、特許を取得していない場合とはどのようなケースかを想像してみましょう。
特許を取得していない場合とは、①・②の2パターンが考えられます。
① 他社が特許を取得する
② 誰も特許を取得しない
< ① 他社が特許を取得する >
他社が特許を取得している状況で、特許に関係する製品・サービスを販売したい場合には「ライセンス料」というものを支払わなければなりません。
ライセンス料とは、簡単にいうと、特許を使わせてもらう条件と引き換えに支払う使用料のようなものです。
とすると、【自社が特許を取得していない場合の売上】は、【自社が特許を取得している場合の売上】から【ライセンス料】を引いたものになります。
なので、
【自社が特許取得している場合の売上】ー【自社が特許取得していない場合の売上】
=【自社が特許取得している場合の売上】ー( 【自社が特許を取得している場合の売上】ー 【ライセンス料】 )
=【ライセンス料】
になり、【ライセンス料】>【特許費用】であれば、特許を取得すべきということになります。
では、ライセンス料はどのように算出するのでしょうか?
答えとしては、【ライセンス料】=【特許が使える状態での売上(=P)】×【ライセンス料率】になります。
ここで、ライセンス料率は、一般的には、特許に関係する製品・サービスの売上は、特許の内容等によって異なりますが、一応の目安として、「平均ライセンス料率」というのがあります。
ここでいう「平均ライセンス料率」というのは、「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書」で開示されている「特許権のロイヤリティ料の平均値」をいい、バイオ、電気、コンピュータテクノロジー等の技術分野ごとに算出されています。
ここで、例えば、化学系の平均ライセンス料率は4.3%となるので、
【ライセンス料】=【生涯売上(=P)】×【ライセンス料率(=4.3%)】>【特許費用(= 150万円) 】となり、
→ P>3488万円
つまり、「特許に関係する製品・サービスの生涯予想売上」が3488万円を超えていれば、自分たちが特許を出さずに他社に特許を取られた場合、自分たちが特許取得していたならばかかったであろう特許費用よりも高い費用を支払わないといけない可能性が高いとのことなので、特許取得した方が良いということになります。
< ② 誰も特許を取得しない >
誰も特許を取得しないというのは、その特許技術が「特許を取る価値がない当たり前の技術」ということになると思います。
ただし、この特許技術が特許が取るほどの価値があるかないかは、特許判断シートでの判断には影響を与えないので、特許判断シートに基づくと、特許が取るほどの価値があるか否かに関わらず、生涯売上見込みが大きいものは、「特許取得すべき」ということになり、ある種無駄な特許申請を行ってしまうことになります。
そこで、重要なのが「AIに特許になる可能性があるかを確認」することです。
これを確認することで、上記のような特許を出して無駄になるケースというのを極力避けることができます。
したがって、特許判断シートにて特許出願すべきと判断された場合であっても、AIが確認するというステップを挟むことで無駄な特許出願を防ぐことができます。
2|『ROI(投資回収率)モデル』からの算出
別の角度から、「投資として回収できるかどうか?」という視点で考える方法もあります。これがいわゆる ROI(Return on Investment:投資回収率) を使った考え方です。
モデル式は下のようになります。
【(特許取得にあたっての)ROI 】> 【粗利】 ÷ 【特許費用】
このROIの数値が高いほど、「かけた費用に対してどれだけリターンがあったか」が大きいということになります。
1、 まず、ROI(投資回収率)を決定 → 300%で固定
ここで、「ROIは300%以上であれば良好な投資」と考えるのが一般的です。
理由としては、一般的な事業投資のROIの目安として、「100%(=投資額と同額の利益)」が最低ラインとされることが多く、それを上回って「200〜300%以上」の回収が見込める投資は、ビジネス的には“成功”と評価されます。
これは、経済産業省 中小企業庁の資料や、企業財務の専門書、またスタートアップ投資の評価基準などでもたびたび引用される水準です。特に知財投資はリスクが高いとされているため、一定のバッファを見込んで300%以上のROIを基準とするのが妥当だとされています。
2、次に「粗利率」から粗利を算出
例えば、〇〇系の粗利率を20%と仮定すると…
粗利 は、(生涯売上)×(粗利率)= P × 0.2 となるので
【ROI(= 300%)】> 【粗利(= P × 0.2)】 ÷ 【特許費用(= 150万円)】
→ P > 2,250万円
というように、「特許に関係する製品・サービスの生涯予想売上」が1,500万円を超えていれば、投資回収的にも特許取得の価値あり、と判断できます。
3| 2つのモデルから…
例えば、化学分野であれば、
| 判断モデル | 特許取得すべき生涯売上の目安 |
|---|---|
| ライセンス料モデル | 3,488万円(ライセンス料率3%を想定) |
| ROIモデル | 2,250万円(粗利率20%+ROI 300%想定) |
つまり、
- 一方の基準を満たせば、特許取得の価値十分あり
- 両方満たしていれば、絶対特許取得すべき
ということになります。
このように、ライセンス料モデルとROIモデルの両面から判断することで、より納得感のある特許判断が可能になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
もちろん、特許を取得すべきか否かの判断は、発明の内容や市場規模、競合状況など様々な要素に左右されるため、固定の評価基準を基づき、個別案件の最良の判断をするのは困難です。ただ、この判断シートを、そのような検討を行う上でのひとつの目安としてご活用いただければ、作成者として大変嬉しく思います。
それでもやっぱり「どうすべきか悩む」という場合は、お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
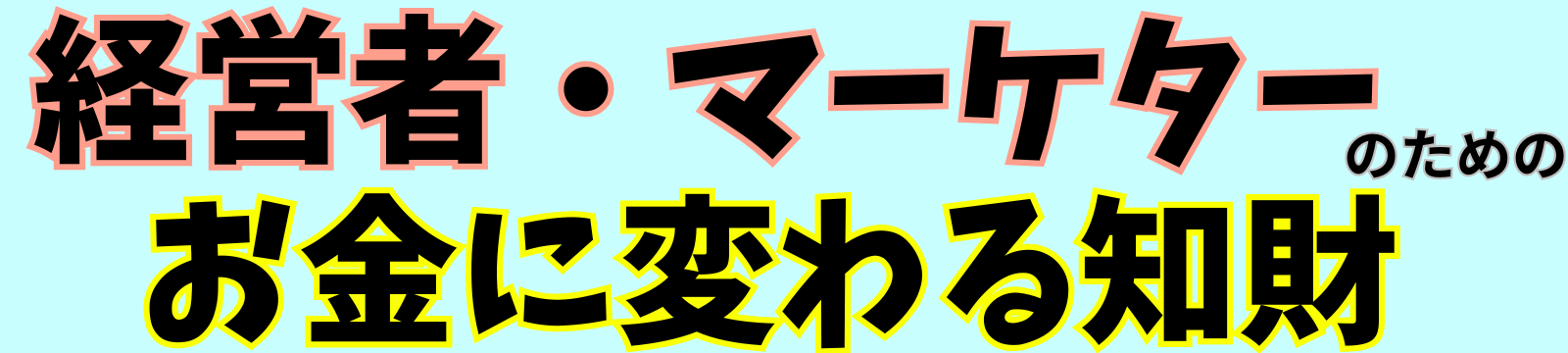
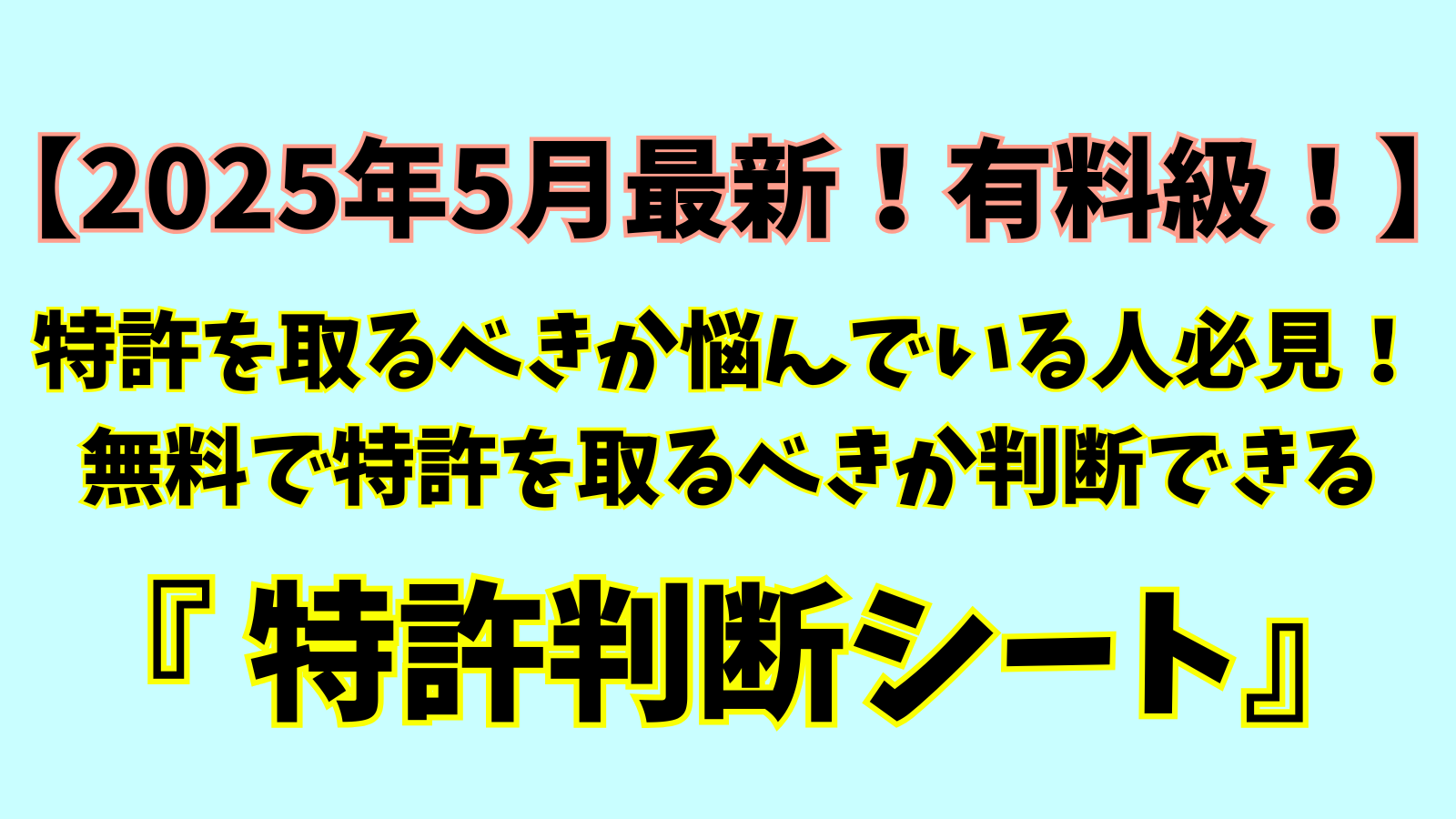
コメント