こんにちは!弁理士のオムレツです。
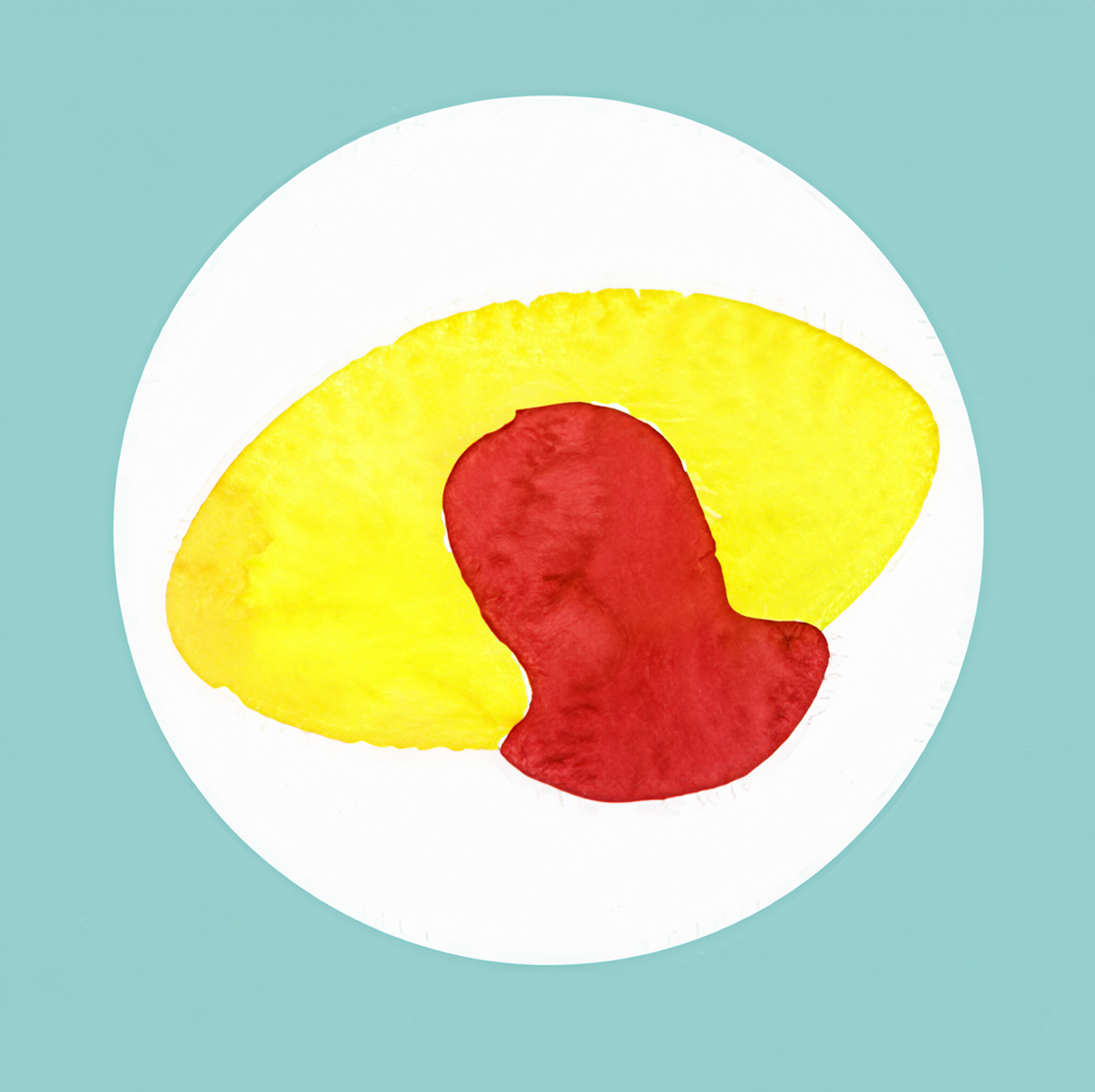
《この記事を読んで欲しい人》
AIで作成した文章・画像の使ってよい範囲が分からない人
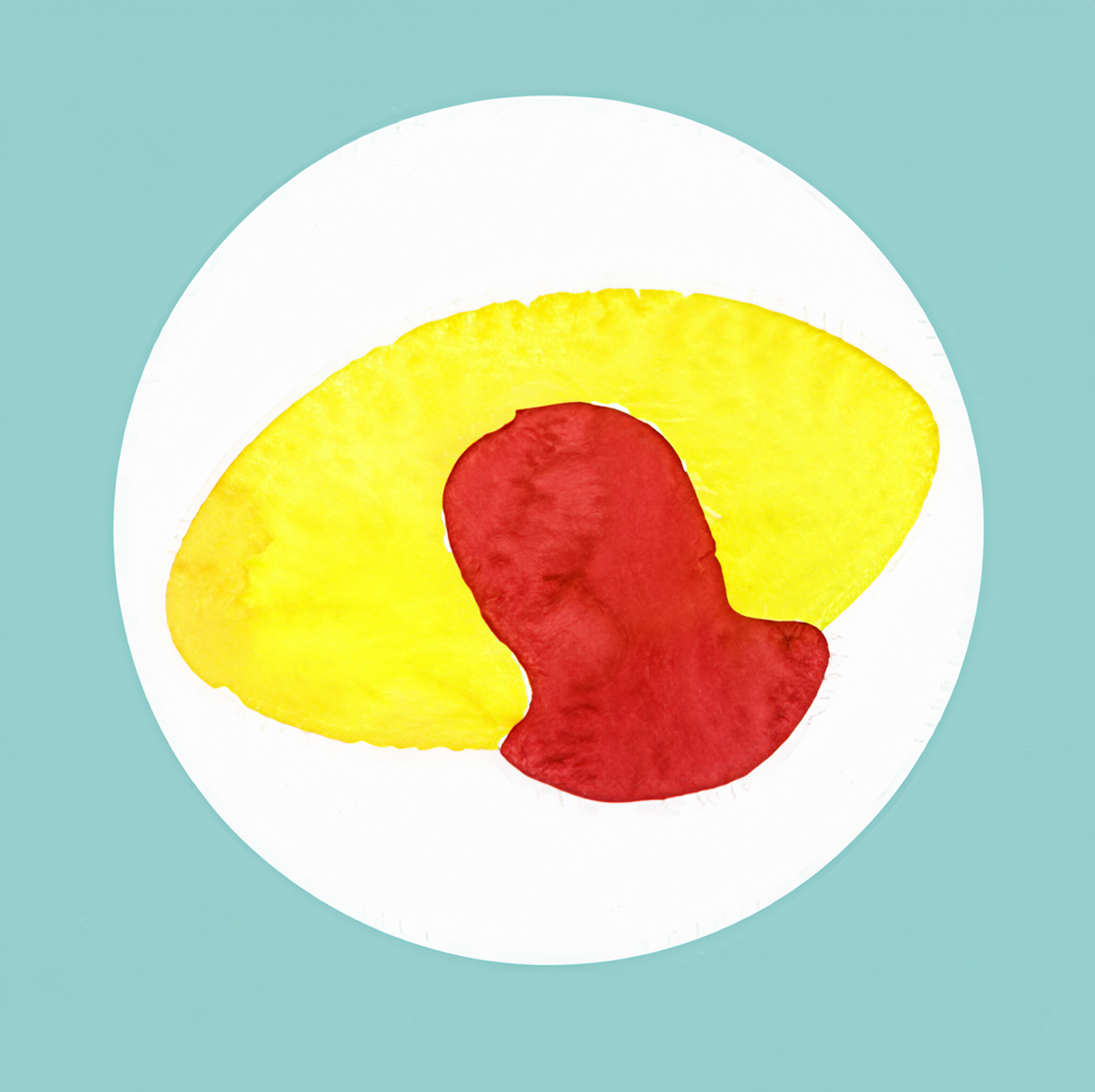 オムレツ
オムレツ《この記事を読んで欲しい人》
AIで作成した文章・画像の使ってよい範囲が分からない人
この記事では、
「AIで作った文章や画像(= AI文章・画像)って、自由に使ってよいの?」「これらを安心して使うには何を確認したらいい?」
そんな疑問を抱えている方に向けて、2025年5月時点の情報に基づいて、AI生成コンテンツの著作権等のルールを分かりやすくまとめた『AI著作権ガイドライン』を作成いたしました。
これを見れば、一発でAIで作成した文章・画像(=AI文章・AI画像)の使ってよい範囲が分かります!
宜しければ是非ご活用ください!
著作権とは?
著作権とは、少し専門的な話をすると、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)」に与えられる権利
なので、日本の著作権法では『著作物』=『人間が創作したもの』が対象です。つまり、AIが自動で作ったものは原則、著作権が発生しません。
「じゃあAIで生成した文章・画像は自由に使ってよいのか」という話になりそうですが、実際はそうではなく、使うAIサービスの「利用規約」を確認する必要があります。
なぜなら、利用規約によって、誰が著作権を有するのか(=著作権の帰属)を決めることが出来るからです。
そこで、主要な生成AIサービスの利用規約を確認し「AI著作権ガイドライン」としてまとめてみました。
これが「AI著作権ガイドライン」!
こちらが「AI著作権ガイドライン」になります!
2025年5月時点の主要な生成AIサービスについてまとめています。
| サービス名 | 著作権の帰属 | 商用利用 | クレジット表記の必要性 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT(無料版) | ユーザーに帰属なし(著作権なし) | 〇(OpenAI利用規約に準拠) | 不要(任意) |
| ChatGPT(有料版) | ユーザーに帰属なし(著作権なし) | 〇 | 不要(任意) |
| DALL·E(画像生成AI) | ユーザーに利用権あり | 〇 | 不要(任意) |
| Adobe Firefly | 著作権はユーザーに帰属 | 〇 | 不要(商用OKと明示) |
| Canva AI機能 | ユーザーに利用権あり | △(内容による) | 任意推奨 |
| Midjourney | ユーザーに利用権あり(有料利用が前提) | 〇(ただし条件あり) | 任意推奨 |
| Bing Image Creator | Microsoftの利用規約に準拠 | △(慎重に判断) | 任意推奨 |
注意点
1. 「著作権」だけでなく「商標権」・「商用利用」にも注意
まず、AI文章・AI画像を利用する際には、「著作権」のみならず、「商標権」・「商用利用」の面でも注意が必要なことを認識しておく必要があります。
2. AIが作っても、指示文(プロンプト)が工夫されていれば著作物になることも
AIに文章・画像を作成させる際の指示文(プロンプト)に創意工夫がなされている場合、その文章・画像の著作権は、その指示者に帰属する場合があります。
そのため、例えば、ネットで「AIで作成した画像です」と書かれた画像が落ちているからといって、誰でも無許可で使用して良いわけではない点については注意が必要です。
3. AIが作っても、有名キャラ等に似ていれば侵害になることも
AIは過去の情報を学習して文章や画像を生成しているため、図らずも、有名キャラやブランドに「なんとなく似ている」ことがあります。これは著作権侵害や商標権侵害になる可能性もあるので注意が必要です。
※ただし、ChatGPTなどは、そのような有名キャラ等に似せた画像を作成することはそもそも出来ない等の理由から、これらが問題になる場合というのは極めて稀であると考えられるため、基本的には、ご自身の感覚で明らかに似ていると思われるAI文章・AI画像の使用を控える程度で、個人的には十分かと思います。
4. あくまで日本での話
これまでの話は、あくまで日本の話ですので、AIで生成した文章・画像を海外で使用する場合には、注意が必要です。
特にネットやSNSにAI文章やAI画像をアップする際には、本来であれば、各国のAI文章・AI画像の著作権・商標権・商用利用の権利を気にする必要があります。
※ ただし、「著作権」「商用利用」については、基本的には、各AIサービスの利用規約によることに加えて、利用規約は各国統一であると考えられるため、日本で安全に使用できている場合には、他の国で問題になるリスクは低いと思います。
また、「商標」の侵害性については、後述と同様、AIで簡単に確認するのが良いと思いますので宜しければご参照ください(AIで商標権の侵害調査・著作権の侵害調査をする場合にはこちらから)。
「AIで作った文章・画像を自由に安全に使う」のための重要な2つのポイント
以上より、いろいろと解説してきましたが、まとめると、「AIで作った文章・画像を自由に安全に使う」上で重要なのは、下記の2点です。
1. 他人の権利を侵害していないか注意する(著作権・商標)
原則として、AI文章・AI画像を利用する場合には、著作権・商標専門の法律事務所に相談することをオススメします。
ただし、利用するAI文章・AI画像の使い方にもよりますが、数多あるAI文章・AI画像の中で、悪質な利用をしていない限り、著作権・商標権の侵害で訴えられるリスクはそこまで高くないことを考慮すると、事前に権利侵害をしていないかを詳細に調べることは、費用と時間を無駄にする可能性が高いです。
そのため、個人的には、重要な案件等でAI文章・AI画像を利用する場合を除き、基本的には、著作権・商標権の侵害性についてはAIで調査することをオススメします。
AIを活用することで、費用をかけることなく、無料で簡易的な調査をすることが出来ます。
AIで商標権の侵害調査・著作権の侵害調査をする場合にはこちらから↓(申し訳ございませんが現在作成中のため今暫くお待ち下さい)
2. 利用するAIサービスの規約を読む(著作権・商用利用)
本来であれば、各AIサービスの利用規約を全て読んだ方が良いですが、読むだけでもかなり時間がかかると思いますので、
個人的には、AIに、使うAIサービスの(著作権・商用利用)での注意点を要約してもらうのが良いと思います。
例えば、Midjourneyの使用を検討している場合に、ChatGPTに「Midjourneyの使用を検討しているのですが、著作権・商用利用での注意点を要約して」と指示を出せば、それだけで(著作権・商用利用)での注意点について、ご自身が利用規約を読まれたときと変わらない程度の十分な回答を得られると思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最近「AIで作った画像や文章って、自由に使ってよいのか」と聞かれることがとても増えました。ChatGPTや画像生成AIなど、便利なツールがたくさんあるからこそ、法律的に“どこまでOKなのか”を正しく知り、トラブルに巻き込まれないことが非常に重要です。
そして、今後も法制度やAIサービスの規約は変わっていく可能性がありますので、常に最新情報をキャッチしながら、安心・安全にAIを活用していただきたく思います(この記事も適宜更新していく予定です)。
「ここに書いてあることだけではよく分からない、、」という方は、気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
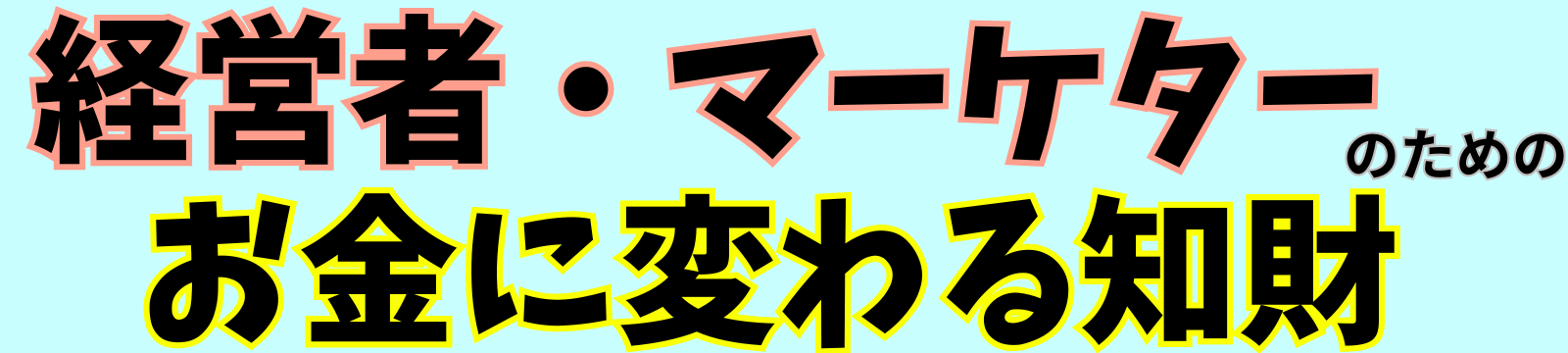
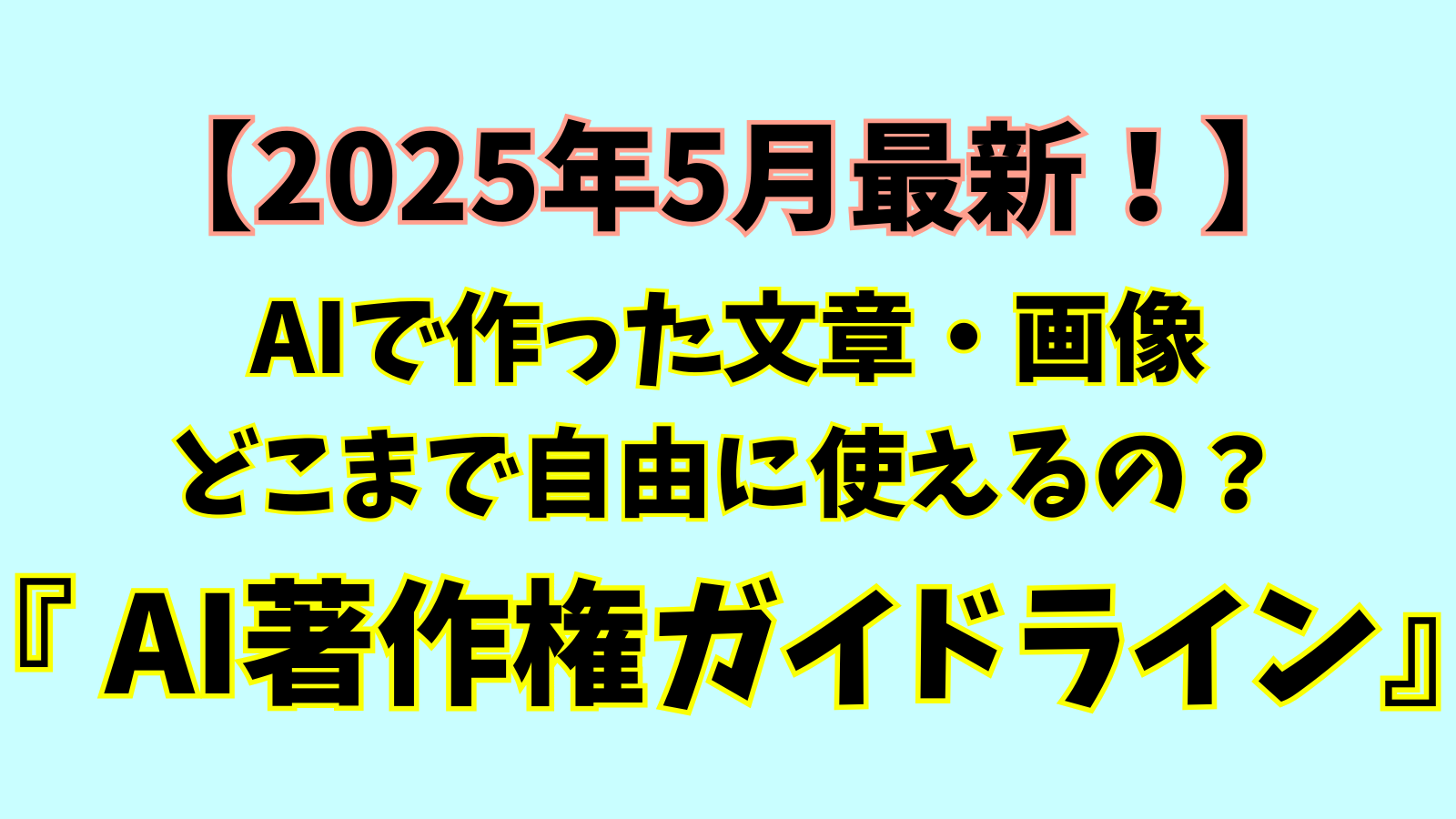
コメント